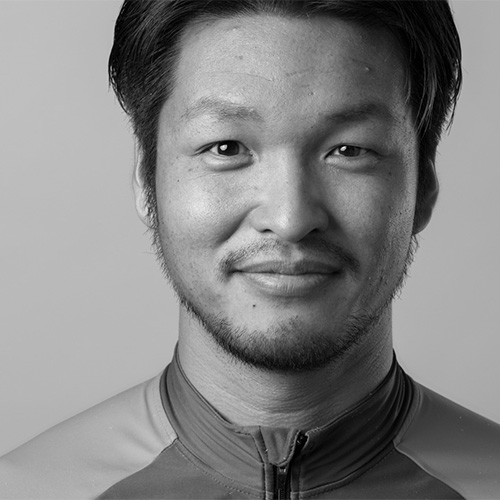10月6~13日にインドネシア・ジャカルタで開催されたアジアパラ競技大会、芦田創選手は男子走り幅跳びで銅メダルを獲得した。競技後、沸きあがってきたのは“満足感”と“悔しさ”という二つの相反する気持ちだったという。果たして、その真相とは――。「パラリンピックをハイパフォーマンスの世界にしたい」と語る芦田選手に迫る。
自らに限界をつくった目標設定


昨年3月、芦田選手は自己ベストの7m15をマークし、一躍世界トップジャンパーの仲間入りを果たした。しかし、その翌週の試合で右足のかかとを痛めてしまう。その後も試合には出場したものの、ケガが完治することはなく、調子を取り戻せないまま2017シーズンは幕を閉じた。
「自己ベストは出たけれど、ケガをしてはなんにもならない。このままがむしゃらにやっていてもダメだなと思いました」
そこで、昨オフはパーソナルトレーナーをつけてウエイトトレーニングに励んだり、自らも専門知識を身に付けようと、1月にはオーストラリアに渡り、オリンピックの跳躍選手を指導しているコーチの下で1カ月間、トレーニングに励んだ。
その結果、これまでは6m台後半を跳んだかと思えば、次には6m台前半に終わるなど、試合の中でも調子に波があった芦田選手だが、今シーズンはどんな状況下でもコンスタントに自己ベスト更新への期待を寄せる「6m80台」を出すことができるようになった。
そんなシーズンの集大成として臨んだアジアパラ競技大会では、シーズンベストの6m88をはじめ、6本中4本で「6m80台」をマーク。そのほかの2本も「6m60台」と大幅に記録を落とすことなく安定した力を発揮。これまでとは明らかに違う成長した自分の姿がそこにはあった。
だが、同時に沸きあがってきたのはアスリートとしての情けなさにも似た悔しさだった。
「記録にも内容にも満足でしたし、目標としてきた6m 80台を続けて出せた自分に合格点を与えていいと思いました。でも、逆に言えば、そんな低いレベルの目標を立てて満足してしまった自分が腹立たしかったんです」
昨年の世界選手権覇者で今大会金メダルのワン・ハオ(中国)は7m53をマーク。それは世界記録まで5cmに迫る大ジャンプだった。世界トップジャンパーでもあるアジアのライバルは、芦田選手の予想をはるかに超える跳躍を見せていたのだ。
「ハオ選手は2本目に7m53を跳ぶと、そのあとはすべてパスしたんです。つまり、僕たちほかの選手が自分を超えることはないだろうと。実際、僕は試合中に『今の自分では彼には勝てない』と思いました。そう思わざるを得ない自分が、本当に悔しかったです」
目標をクリアしたことへの満足感。そんな満足感に対する悔しさ。どちらの感情も芦田選手には次への糧となるものだった。
リオで感じた「パラリンピック」への感情

芦田選手にとって初めてのパラリンピックとなった2年前のリオデジャネイロ大会。結果は、予選落ちで12位。当時の自己ベスト(6m84)には遠く及ばない6m52に終わり、ファイナリスト8人に残ることができなかった。
そんな初めての世界最高峰の舞台は、芦田選手にとってどんなものだったのか。改めてそのことを聞くと、意外な答えが返ってきた。
「正直に言えば、あの時は『パラリンピックって、こんなものなんだな』と思いました」
リオ以降、芦田選手のクラスの走り幅跳びはさらにレベルが上がり、現在、世界の舞台でメダルを獲得するには7m台後半の記録が必要となる。より「ハイパフォーマンスの世界」に近づきつつあり、そこに挑戦することへのやりがいを感じている。
しかし、リオ当時のトップジャンパーたちの記録は7m前半で、メダルのボーダーラインは、7m10前後。それは高校時代にインターハイを目指して陸上競技部に所属していた芦田選手にとっては、決して満足できるものではなかった。実は日本の中学生の最高峰である「全国中学校体育大会」ともなると、優勝ラインが7m10前後なのだという。
「実際、障がいがありながら7mを跳ぶって、簡単なことではありません。まさに才能であり習得した技術の賜物。でも、障がいがあるからそれでいいという考えが僕は好きではない。純粋にアスリートとして『すごい』と思ってもらいたい。世界最高峰と謳っているパラリンピックは、そういう世界であるべきだと思うんです」
そして、「ただ」という言葉を添えて、こう続けた。
「リオでは自分は決勝にさえ進むことができなかったわけで、それは言い訳にはできません。まだ本格的に幅跳びを始めて1年半だったとはいえ、自分への不甲斐なさでいっぱいでした」
今の自分はとうてい言える立場にはないことは十分にわかっていながら、それでもあえて言葉に出すのは、パラリンピックをオリンピックと同じように「ハイパフォーマンスの世界」に位置付けたいという思いの強さにほかならない。
海外を拠点に移す2つの理由


今年のアジアパラでの競技が終わったその日、芦田選手はあることを決意した。拠点を海外に移すことにしたのだ。それは今年1年間、ずっと考えてきたことだった。
アジアパラの9カ月前、今年1月にオーストラリア・シドニーで、芦田選手はあるコーチの下で練習生としてトレーニングを積んだ。オリンピックの跳躍選手を指導するアレックス・スチュワートコーチだ。彼の指導は、それまで芦田選手が国内でやってきたこととは異なっていた。
これまで芦田選手がまず念頭に置いていたのは「助走」だった。助走のスピードを高め、安定させることで、踏み切りの際にパワーが生まれ、それが記録につながるという考えだった。だが、その跳躍では少し限界を感じつつあったという。そんな中で臨んだオーストラリア留学での指導では、「助走」ではなく、まず「踏み切り」を考えるものだった。
「アレックスコーチの指導で最も重要視していたのは理想の踏み切りをすることでした。その踏み切りをするための助走なんだと。それがすごく新鮮で、自分にしっくりきたんです。もともと僕は走るのが得意というわけではなくて、体のバネを使ったバウンディング能力の高さを生かすタイプ。だから踏み切りを重視した考え方の方が合っているのかもしれないなと思いました」
そこで帰国後、今シーズンはこれまで身につけた技術と、シドニーで新たに知った知識をミックスさせた跳躍にチャレンジしようと考えた。しかし、シーズンを通して試行錯誤してきたが、二つの要素をミックスさせることはやはり難しく、どちらかを選ぶ必要があると感じたという。そこで芦田選手は、オーストラリアで新たな挑戦をすることを決意したのだ。
そして実はもう一つ、芦田選手が拠点を海外に移そうと決めた理由がある。真のトップアスリートを目指すために“本当の自分”と向き合うためだ。
「パラリンピックというと、どうしても社会性と結びつけられてしまい、『どう障がいを乗り越えたのか』ということで注目される。でも、僕は純粋にアスリートとして競技力で注目してほしいと思っているんです。そのためには自分が真のトップアスリートにならなければいけない。でも日本は今、2020年に向けて機運が高まっていて、それ自体はとても素晴らしいことですが、周囲からの期待に乗せられるようにして、どうしても自分を大きく見せるような言葉を求められてしまう。それは僕にとって本意ではありません。ならば海外に行って雑念のない状態で、競技に専念したいと思ったんです」
芦田選手の2020年東京パラリンピックでの目標は金メダルであることは間違いなく、そこにブレはない。しかし、今の自分は声高らかに“金メダル宣言”ができる立場ではないとも思う。世界における自分の立ち位置はどこなのか。今はその現実を直視し、黙々とトレーニングに励む時。芦田選手はそう思っている。
「来年11月の世界選手権では、新たな芦田創のジャンプをお見せできると思います。僕自身、すごく楽しみなんです!」
強い信念を持ち、独自の路線を進む孤高のアスリート芦田創。自分自身が求める「真のアスリート」となるべく、新たな道に挑む。

-

芦田 創(あしだ はじむ)
陸上競技T47クラス/トヨタ自動車所属
1993年12月8日、大阪府生まれ。
幼少期、右上肢にデスモイド腫瘍が見つかり、
その後、摘出手術や放射線治療の中で機能障害となる。
半ば諦めた気持ちで好きな陸上を始めると、奇跡的に腫瘍の進行が止まった。
高校では陸上部に所属。早稲田大学では3年間趣味程度に陸上を続けていたが、
就職活動の折に障がいを負った意味を見出す中で、再び本格的に陸上を始めることを決意。
4年春から同大学競走部の礒繁雄監督に師事し、2015年からは本格的に走り幅跳びを始める。
2016年リオデジャネイロパラリンピックでは男子走り幅跳びで12位、
男子4×100mリレー(T42−47)では銅メダルを獲得した。
2017年3月シドニー・キャンベラで行われた
サマー・オブ・アスズ・グランプリで自己ベスト7m 15をマーク。
2018年10月のアジアパラ競技大会では男子走り幅跳びで銅メダルを獲得した。